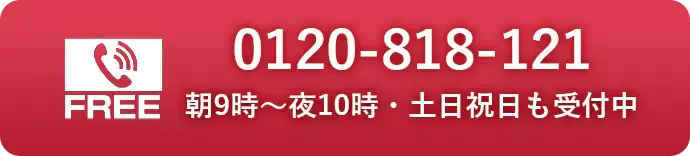- 退職代行を利用して退職したあと、健康保険証や社員証、カードキーなどの返却物はどうすればいいですか?
-
最終出勤時にご返却いただくのがよいのです。ただし健康保険証を退職日まで使用したいなどの場合は、後日依頼者の方から会社宛に郵送などでご返却いただいても問題ありません。
返却方法について、ご自分で確認するのが不安な方については、弁護士が会社に連絡をとり、返却手続について確認することも可能です。
- 退職代行を利用して退職したら、会社から損害賠償請求を受けませんか?
-
退職代行を、弁護士と弁護士以外のいずれに依頼するかによって、会社から請求を受けるリスクの程度が変わります。
民間企業などの弁護士以外が提供する退職代行サービスでは、退職の意思を伝えることしかできず、会社から「退職するなら損害賠償を請求する」などと主張された場合(裁判所へ訴えられた場合はもちろん、いわゆる任意交渉の場合も含みます)の対応を代理することはできません。
これらの退職代行サービスを利用した場合、この弱点を知っている会社は、「損害賠償請求をけしかけさえすれば、退職代行業者は手を引き、本人を引きずり出すことができる」と考えるでしょう。つまり、考えようによっては、自分で退職する場合以上に請求を受けるリスクが高まるのです。他方、弁護士による退職代行サービスであれば、上記のような弱点が原因で会社からの請求を誘発することはありません。
そもそも、「期間の定めのない雇用契約」については、労働者が希望すれば、法律上、理由を問わず退職することができる(民法第627条第1項後段)ため、退職すること自体を理由に損害賠償責任を負うことは原則としてありません。「期間の定めのある雇用契約」については、雇用期間内に退職し、かつ、依頼者の方に何らかの過失があるような場合には、損害賠償請求を受ける可能性もあります(民法第628条後段)が、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方が会社から損害賠償請求を受けることなく、かつできるだけ早期に退職できるよう弁護士が交渉いたしますのでご安心ください。
- 弁護士に依頼しても退職できないことはあるのでしょうか?
-
雇用契約には、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」の2種類があります。
まず、「期間の定めのない雇用契約」については、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です(民法第627条第1項後段)。
また、2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から、会社に退職の意思表示を行って即時の退職を申し入れると、多くの会社は退職に合意します。一方で、「期間の定めのある雇用契約」については、原則として雇用期間が満了するまで一方的に退職することはできません。
しかし、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められます(民法第628条前段)し、特段やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。
- 退職代行を使って後悔することはありますか?
-
退職代行を使って後悔する理由としては、主に下記が挙げられます。
- 対応してもらえない内容(有給休暇消化の交渉など)があった
- 会社側から「損害賠償を請求する」などと言われ、トラブルに発展した
- 費用が高かった
民間企業による退職代行サービスでは、「退職の意思を伝えること」しか対応してもらえません。
そのため、「有給消化の交渉」、「損害賠償請求を示唆された場合の対応」などをまとめて任せることはできず、これらを解決したい場合には自分で対応するしかないのです。費用の安さに惹かれて民間企業の退職代行サービスを利用したが、トラブルになり退職することができず、結局弁護士へ依頼することとなり二重に費用がかかった、というケースも見受けられます。このように、民間企業による退職代行サービスでは、「なるべく有給を消化してから退職したい」とお考えの方はもちろん、そうでない方の場合でも、思わぬトラブルに巻き込まれ、後悔する可能性があります。
安心して退職を実現するために、弁護士による退職代行サービスのご利用をおすすめします。
- 退職代行のデメリットは何ですか?トラブルに巻き込まれることがありますか?
-
民間企業が提供する退職代行サービスには、いくつかデメリットがあり、トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
よくあるデメリットとして、民間企業の退職代行サービスは「退職の意思を伝えることしかできない」という点が挙げられます。
「それだけで十分なのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょうが、たとえば下記のようなトラブルが想定されます。- 有給休暇の消化が認められない
- 退職月の給与や退職金が支払われない
- 損害賠償を請求される
上記のトラブルが発生した場合、民間企業は何も対応できません。
弁護士法という法律によって、弁護士以外が交渉などの法律事務を取り扱うことは原則として違法とされているからです(弁護士法第72条本文)。これに反した場合には罰則もあり、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります(弁護士法第77条第3号)。
利用者まで罪に問われることは原則ありませんが、警察の事情聴取を受けたり、本来の目的である退職ができなかったりする可能性があります。また、労働組合が提供する退職代行サービスもあり、これらは「団体交渉権があるので、会社と交渉できる」と謳っています。
しかし、このような労働組合は、退職代行サービスの提供だけを目的として形式的に作られたものである場合がほとんどです。つまり、実態としては上記の民間企業とほぼ同様な組織にすぎないため、団体交渉権は認められず、やはり弁護士法に違反するのではないか、という指摘もあります。
さらに、仮に交渉ができるとしても、有資格者である弁護士と比較すれば、労働法以外も含めた法的知識の幅広さや、会社に対する牽制の効果の違いは歴然でしょう。一方で、弁護士による退職代行サービスを利用する場合、上記のデメリットやトラブルを心配する必要はありません。
会社側も、弁護士が付いているのなら大事にはしたくないでしょうし、万が一トラブルになったとしても、弁護士であれば交渉してうまく対応することができます。
- 退職代行の金額はいくらですか?相場はどのくらいですか?
-
退職代行サービスの金額は、民間企業や法律事務所などの運営元ごとに金額や相場が異なります。
一概にはいえませんが、民間企業や労働組合が運営元であれば、20,000円~50,000円。法律事務所の場合は、50,000円以上が相場であるといえるでしょう。金額面だけを考えれば、民間企業の退職代行サービスが利用しやすいかもしれません。
しかし、民間企業が行えるのは、あくまで依頼者の方の代わりに退職の意思を伝えることだけです。
もし、「退職するなら損害賠償を請求する」、「1ヵ月経過しないと退職は認めない」などと言われた場合、民間企業では何も対応できません。弁護士法という法律によって、弁護士以外が交渉などの法律事務を取り扱うことは原則として違法とされているからです(弁護士法第72条本文)。詳しくはこちら:退職代行のデメリットは何ですか?トラブルに巻き込まれることがありますか?
つまり、ひとくちに退職代行サービスといっても、取り扱える内容には大きな差があり、当然ながら、相場の高いものほど幅広いサービスを受けられるのです。安心してスムーズに退職したい方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると、退職の意思を伝えてくれるだけでなく会社との交渉や書類のやり取りも行ってくれますし、有給消化の交渉、やり残した業務の引継ぎ、会社に置いている私物の管理なども相談できます。
なかには、退職の話をすると退職者が不利になる条件を提示してくる会社もありますので、そういった場合も弁護士がいれば最後まで安心です。
- 退職代行を利用して退職した場合、会社の健康保険はいつまで利用できますか?
-
健康保険証が利用できるのは退職日当日までです。この期日は、自分で伝えて退職した場合も変わりません。
たとえば、8月31日付で退職した場合は、健康保険証が使えるのは8月31日の23時59分までとなり、9月1日からは使用できなくなります。
使用できなくなった保険証で医療機関を受診すると、後日、保険組合が負担した医療費(7〜8割)を返還請求されるため、退職日の翌日以降は使用しないようにしましょう。
保険証は速やかに会社へ返却する必要がありますが、その返却手続も退職代行業者を通して行える場合があります。
- 退職代行を利用する際、退職理由は正直に伝えるべきですか?
-
伝えることをおすすめします。
退職理由をはじめ、退職に関わる事情はすべて把握しておいてもらったほうが、手続をスムーズに進めてもらいやすいからです。なお、退職代行サービスの運営側が、会社に退職の意思を伝える際は、「一身上の都合で」と話すことが一般的です。
人間関係のトラブルや会社への不満などを正直に伝えてしまうと、会社側が感情的になり、退職手続が進まなくなるおそれがあるためです。
また法律上も、具体的な退職理由を伝えるは義務などはありません。
- 試用期間中でも、退職代行を利用することはできますか?
-
利用できます。民法では、退職の意思を伝えてから最短2週間で退職できる(※)と定められています。
試用期間中であっても、すでに法的な労働契約は成立しているため、上記のとおり退職の意思を伝えれば、会社側にこれを阻止する権利はありません。「入社してすぐだから、言い出しづらい…」、「求人内容と実際の業務が全然違う…」といった理由でも、退職代行を利用すれば、上司や同僚と顔を合わせることなく、スムーズに退職手続を進めることが可能です。
※正社員など、期間の定めがない雇用契約の場合。期間の定めがある契約社員などの場合も、やむを得ない理由があれば、ただちに契約解除が可能。
- 退職代行を利用して退職すると、次の転職活動で不利になりますか?
-
転職活動で不利になることは、基本的にないと思います。
そもそも、退職の経緯は自分から話さない限り伝わることはないと思われます。また、個人情報保護法の観点から、応募先の企業が前職の会社に退職理由を問い合わせるケースもほとんどなくなっています。
退職代行を利用したという事実は、あくまでも円満退職が難しい状況であったことを示すものですし、応募者の能力や経歴とは無関係だといえます。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121